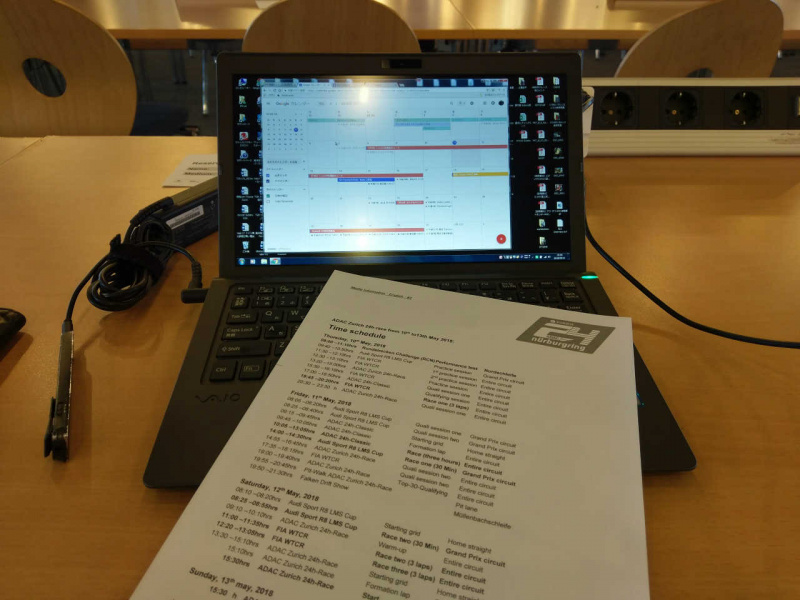「新車開発の聖地」としてもよく知られるドイツ・北西部に位置するニュルブルクリンク。その歴史は非常に古く、オールドコースと呼ばれるノルドシュライフェは、第2次世界大戦前の世界不況の時代にヒトラーの提案により建設された巨大サーキットだ。
サーキットと言いながらも、ヨーロッパの一般地方道に似たレイアウトで、1周約20.8kmと距離も凄いが、標高差300m、大小170を超えるコーナーは、低速から超高速域のスピードレンジまで多様多種。さらに路面状況はほとんどの路面が波打っており、埃っぽく滑る上、コース幅も狭くエスケープゾーンもほとんどない…など、世界有数の難関コースと呼ばれている。ちなみに日本のサーキットと比較してみると、富士スピードウェイは4.563km/高低差40m/16コーナー、鈴鹿サーキットは5.807km/高低差約40m/20コーナーと、ニュル巨大さが解るだろう。
車両の総合的な性能がラップタイムに反映されやすいことから、世界の主要自動車メーカーのほとんどは、ここでテストを行なっている。コースの近郊には各メーカーのテストラボが存在し、開発途中のニューモデルのテストカーと遭遇する事も多々ある。
ニュルブルクリンクは誰でも走行料を払えば走行が可能だが、プロドライバーに話を聞くと「ニュルは楽しいね……と言っているうちは本当のニュルではなく、走れば走るほど“怖さ”が見えてくる」と語る。百戦錬磨のプロドライバーですら追い込んでしまうニュルブルクリンクは「緑の地獄」と呼ばれるが、クルマだけでなくドライバーにとっても過酷なコースなのである。
そんなニュルブルクリンクを舞台とする、「ニュルブルクリンク24時間耐久レース(正式名・ADAC Zurich 24h-Rennen)」は、今年で46回を迎える。170台を超えるマシンが、F1も開催された1周約5.1kmの「グランプリコース」と、1周約20.8kmの「ノルドシェライフェ」を合体させた約25kmのコースを使って争われる。
筆者は2005年に初めて取材に来てハマり、何回か行けなかった年もあったが、気が付けば10年以上ニュル24時間詣を続けている。
なぜ世界選手権でもないドイツの草レースにハマったのか? 近年はワークス/セミワークスチームや著名なプロドライバーの参戦、マシンの高性能化によりプロフェッショナル化も進んでいるものの、170台以上の様々なカテゴリーのマシンがコースを一堂に走るシーン、チームの規模に関係なくひとつのピットを複数台でシェアするスタイル、過酷なレースを生き抜くためには速さや耐久性だけでなく“運”も大事なこと、他のレースに比べると“強い者が勝つ”という単純明快なコンセプトに共感したからだと思う。
更に日本車/日本人がドイツのアウェイな場所で孤軍奮闘しているシーンを見たことも大きいかもしれない。実は筆者が初めてニュル24時間に行った2005年は、日産スカイラインGT-Rで参戦する最後の年、スバルインプレッサWRX STIがニュル24時間に初参戦(当時はプローバ)、そして、あまり知られていないがレクサス実験部がレクサスRX450h(日本名・トヨタハリアーハイブリッド)や自動車雑誌REVスピードがスズキ・スイフトスポーツで参戦していた。
その後、2007年にGAZOO Racing(現・TOYOTA GAZOO Racing)、2008年かSTIが参戦しているが、どちらも専門のレーシングチームではなく、量産車開発を行なうメンバーで構成されていた。その意図は、勝ち負けだけでなくニュル24時間を「開発の場」としてレースを行なうためである。
トヨタ/STI共に「いいクルマはテストコースだけでは生まれない。“戦う場”に身を置くことでクルマも人も育つ」と言う考えを持って参戦を行なう。実はこの手法、自動車黎明期に各メーカーが行なっていたことと同じ、デジタルが発達した現在だが、いくらいいハードが揃っていても、人が進化しない限りはいい物には仕上がらない。そこでトヨタ/STIはクルマ作りの“原点”に戻ったのだ。いつの時代も“箱庭”のようなテストコースの中だけでは「いいクルマ」は生まれない。
ただ、ニュル24時間は色々な意味で “異常”な事ばかりである。そんなリスクを侵しても、自動車メーカー、開発チーム、そしてドライバーがこのレースに挑戦する本当の意味はと言うと、筆者は「クルマとヒトを育てる」だけの理由ではないような気がしている。
長年ニュル24時間の取材をして解ったのは、決して口には出さないものの常勝の欧州勢に対して「お前らに負けるもんか!!」と言うような『日本人魂』を感じることである。
恐らく、ニュルには温和な日本人ですら刺激する『何か』が存在すると思っている。その魅力から逃れられないからこそ、毎年ニュルを目指すのかもしれない。それは参戦する側だけでなく、取材する側も同じである(笑)。
(山本 シンヤ)
あわせて読みたい
Source: clicccar.comクリッカー